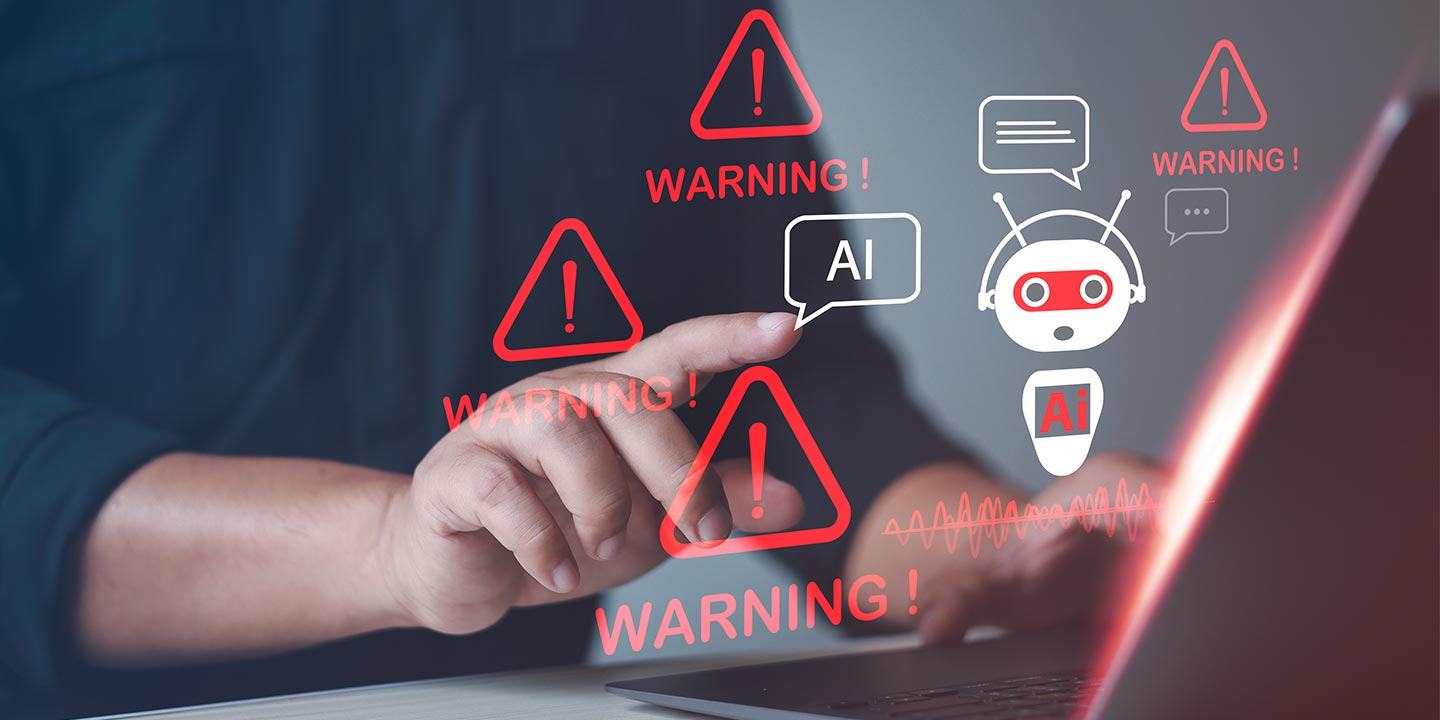-
タグ
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR
AIが急速に普及するなか、AIに対する脆弱性を狙ったセキュリティリスクに注意する必要があります。一方でAIを活用した高度なセキュリティが注目されているのが現状です。
本記事では、AIセキュリティ対策について、企業のIT・セキュリティ担当者が知っておくべきリスクと具体的な対策を解説します。
AIセキュリティ対策が今、なぜ重要なのか
現代のデジタル社会において、AIセキュリティ対策の重要性が急激に高まっています。重要性が増している背景には、サイバー攻撃の進化とAI技術の普及の大きな2つの変化があります。
サイバー攻撃は2000年代初頭の単純なメール感染から大きく様変わりしました。現在では攻撃手法が洗練され、企業や個人から身代金を要求するランサムウェア攻撃が深刻化しています。
一方で、ディープラーニング技術の発展により、AIの能力は飛躍的に向上しました。また、テキスト、画像、音声など多様なコンテンツを生成できるAIが急速に社会に浸透しています。しかし、便利なAI技術は、利用の際に機密データが流出するリスクのほか、悪意ある者に悪用される危険性も秘めており、新たなセキュリティリスクを生み出しています。
「守り(Security for AI)」と「攻め(AI for Security)」の視点
AIセキュリティには、「守り」と「攻め」の2つの重要な視点があります。※1
「守り」の視点であるSecurity for AIは、AI技術そのものを安全に活用するための取り組みです。Security for AIは、AIシステムを利用する際に発生しうる機密データの流出リスクや、悪意ある者によるディープフェイク技術などを用いた巧妙な攻撃から組織を守ることが目的です。
一方、「攻め」の視点であるAI for Securityは、高度化するサイバー脅威に対抗するためにAI技術を積極的に活用するアプローチです。AI for Securityは、従来の人的作業では困難だった潜在的な攻撃ルートの予測や分析を可能にし、検出困難だった未知の脅威や、日々進化し続ける攻撃パターンを効果的に識別できることが特徴です。
さらに、検出から対応までのプロセスを自動化することで、人的介入による遅延を大幅に削減し、セキュリティ運用の効率性を飛躍的に向上させることができます。
AI活用に潜む主なセキュリティリスク

AI活用にはセキュリティ上のリスクがあることに注意しなければなりません。AI活用には主に次のリスクが潜んでいます。
- 機密情報や個人情報の入力による情報漏えい
- AIが生み出す不正確な情報(ハルシネーション)
- 生成物が第三者の権利を侵害する可能性
- AIシステムを狙った新たなサイバー攻撃
それぞれのリスクの内容を解説します。
機密情報や個人情報の入力による情報漏えい
AI活用における深刻なセキュリティリスクの1つが、機密情報や個人情報の漏えい問題です。AIシステムは高精度な学習と予測を実現するため、膨大な量のデータを必要とします。
一方で、データ処理過程において、重要な情報が意図せず外部に流出してしまう危険性が常に存在しています。特に企業の機密データや顧客の個人情報など、機密性の高い情報を扱う場合は情報漏えいリスクが極めて深刻な問題となりかねません。
情報漏えいの経路は多岐にわたり、外部からの不正アクセスによって、システムの脆弱性が悪用されるケースが代表的です。また、組織内部からの脅威も無視できません。内部関係者が不正な手段でAIシステムにアクセスし、データを持ち出すケースもあります。
AIが生み出す不正確な情報(ハルシネーション)
生成AIは、人間が書いたかのような自然で説得力のある文章を作成する能力を持っています。一方で、AIは過去に学習したデータを基に回答を構築しますが、その過程で事実とは異なる情報や完全に架空の内容を、あたかも真実であるかのように巧妙に組み立てることがあります。これがハルシネーション現象の本質です。
海外では、生成AIが著名な政治家に関して事実と異なる経歴情報を生成し、その誤情報がインターネット上で広く拡散される事態が発生しました。結果として名誉毀損問題に発展し、社会的な混乱を招いています。
ハルシネーションのリスクを回避するためには、AIが提供する情報を盲信せず、常に参考程度に留めることが重要です。人間による慎重な事実確認プロセスを必須とする体制構築が、安全なAI活用のポイントです。
生成物が第三者の権利を侵害する可能性
AI技術の活用において、生成されたコンテンツが第三者の知的財産権を侵害するリスクも注意が必要です。生成AIは膨大な既存のデータから学習を行うため、出力物が既存の著作物と類似してしまったり、無意識のうちに既存作品に依拠した内容を作り出してしまったりする可能性があります。
権利侵害を防ぐためには、たとえば文章コンテンツを外部に発信する場合、AIが生成した原稿を人間が詳細に検証し、必要に応じて大幅な修正を加えることが重要です。また、より安全なアプローチとして、AIには文章の骨組みや構成のみを作成させ、実際の執筆作業は人間が担当する手法も有効です。
画像コンテンツは、特に視覚的な類似性が判断しやすいため、より一層の注意が求められます。既存の作品やブランドイメージとの類似性を避けるため、厳格なチェック体制を整備することが必要です。
AIシステムを狙った新たなサイバー攻撃
AI技術の普及に伴い、従来のサイバー攻撃とはまったく異なる新しい脅威が登場しています。脅威の1つがプロンプトインジェクション攻撃です。プロンプトインジェクションは、攻撃者が巧妙に設計された指示文を生成AIに送信することで、攻撃者の意図した不正な応答を生成させたり、機密情報を不正に取得したりします。
特にAIがデータベースや外部システムと連携している環境では、本来アクセスできないはずの重要情報が漏えいする危険性が高まります。
もう1つの重要な脅威が、データポイズニング攻撃です。データポイズニング攻撃は、AIモデルの学習段階において、意図的に偽造された有害なデータを混入させることで、モデルの判断能力を操作します。
AIのセキュリティリスクをめぐる規制動向
AIのセキュリティリスクに対する社会的関心の高まりを受けて、世界各国で規制整備が加速しています。国際的な基準として、米国商務省の国立標準技術研究所(NIST)が策定した「AI Risk Management Framework | NIST」※2が注目されています。この枠組みは、AIに関するリスクを管理し、信頼できるAIシステムを構築するための7つの特性(安全、安心、公平、プライバシー強化など)を示しています。
また、米国では、AI技術がもたらす恩恵を最大化しつつリスクを効果的に管理することを目標とした大統領令「The Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence」※3が発表されました。
日本においても、総務省と経済産業省が共同で「AI事業者ガイドライン」※4を策定しました。ガイドラインは、技術革新の促進と潜在的なリスクの軽減を同時に実現する統一的な方針を示すことで、産業界と規制当局が協力してAIガバナンスの枠組みを構築することを目指しています。
企業が今日から始めるべきAIセキュリティ対策
生成AIの活用が進むなか、企業は早急なセキュリティ対策が求められます。社内ガイドラインの策定やセキュリティ教育の実施、人間による最終判断が可能な仕組み作りが必要です。
また、セキュリティ機能が搭載されたAIサービスを選定することも欠かせません。今日から始めるべきAIセキュリティ対策を解説します。
AI利用に関する社内ガイドラインを策定する
AIシステムを組織に導入する際には、情報管理と機密データの適切な取り扱いに関する明確な指針を確立することが不可欠です。統一されたガイドラインにより、従業員は迷うことなく安全にAI技術を活用でき、同時に潜在的なセキュリティリスクを事前に回避できます。
犯罪に関連する行為や他者の個人情報を無断で利用する行為、さらには偽造画像や音声を作成するディープフェイク技術の悪用などを明確に禁止する条項が必要です。また、AIシステムへの入力データに関する制限事項も、ガイドラインとして含めなければなりません。
実際のガイドライン作成においては、経済産業省と総務省が共同策定したAI事業者ガイドライン※4や、日本ディープランニング協会が提供する生成AI利用指針※5などが、実用的な参考資料として活用できます。
従業員へのセキュリティ教育を徹底する
AIセキュリティ対策において、技術的な防御措置と同じく重要なのが従業員に対する継続的な教育プログラムです。
効果的なセキュリティ教育は、単発的な研修ではなく定期的かつ体系的なアプローチが求められます。従業員が最新の脅威動向やAI特有のリスクの理解を深めることで、組織全体のセキュリティ意識が底上げされます。
実践的な対応能力を養うためには、セキュリティインシデントが実際に発生した際の対応訓練やシミュレーション演習も欠かせません。机上の知識だけでなく、緊急時における迅速で適切な判断力と行動力を身につけることで、被害の最小化が可能です。
従業員一人ひとりがセキュリティの重要性を理解し、日常業務において適切な行動を取ることで、AI活用における安全性が向上します。
AIの出力を鵜呑みにせず人間が最終判断する
効果的なセキュリティ管理には、AIシステムへの入力データと出力データ双方に対する厳格な管理体制が必要です。特に生成されたコンテンツを外部に公開する前には、複数の観点からの検証が欠かせません。
情報の正確性検証はもちろん、既存の著作物との類似性チェック、さらには社会的・倫理的な問題がないかの確認など、多角的な審査プロセスを設けることで、AI利用に伴う様々なリスクを軽減できます。
また、AIシステムの利用状況を定期的に記録・分析し、通常とは異なる使用パターンや問題のある操作がないかを常時チェックすることも必要です。人間の専門的判断力とAI技術を適切に組み合わせることで、技術の恩恵を享受しながら安全性を確保する理想的なバランスが実現できます。
セキュリティ機能が搭載されたAIサービスを選定する
企業がAIシステムを導入する際には、業務効率や生産性の向上だけでなく、セキュリティ面での慎重な評価が不可欠です。AIサービス選定においては、各ベンダが提供するセキュリティ機能の詳細な比較検討が必要です。
データの暗号化技術の強度、ユーザアクセス権限の管理システム、監査機能の充実度など、自社のセキュリティ要件と照らし合わせて総合的に評価することが求められます。セキュリティ機能が不十分なシステムを選択してしまうと、後々深刻なリスクに直面する可能性があります。
特に、機密性の高い企業情報や顧客データを取り扱う場合には、より慎重な配慮が必要です。入力されたデータがAIの学習プロセスに無断で利用されることを防ぐオプトアウト機能により、組織の重要情報が意図せず外部に流出したり、ほかの利用者に間接的に共有されたりするリスクを効果的に回避できます。
AIを活用した次世代のセキュリティ防御策

AIセキュリティに対するリスクに注意するだけではなく、AIを活用した次世代のセキュリティ防御策を講じることも大切なポイントです。AIを活用することで、未知のマルウェアやサイバー攻撃の兆候を検知できるほか、セキュリティインシデント対応の迅速化と自動化も可能です。
それぞれの防御策を詳しく解説します。
未知のマルウェアやサイバー攻撃の兆候を検知
AIを活用した次世代セキュリティ防御は、機械学習アルゴリズムの活用により、膨大な量のデータをリアルタイムで処理し、通常とは異なる不審な活動パターンを瞬時に識別することが可能になりました。
フィッシング詐欺やマルウェア感染などの脅威を従来よりもはるかに早い段階で発見でき、被害拡大を防ぐための迅速な対応が実現できます。
AIセキュリティシステムの最大の強みは、過去の攻撃事例から学習し続ける適応能力です。蓄積された脅威データを基に新たな攻撃手法に対しても柔軟に対応できるため、日々進化するサイバー脅威に対する防御力が継続的に向上します。
さらに、過去のシステム設定ミスやセキュリティ規則違反の事例を分析することで、現在の設定がどのような攻撃リスクを生み出す可能性があるかを評価できます。
セキュリティインシデント対応の迅速化と自動化
AIを統合したセキュリティオートメーション技術は、現代のサイバーセキュリティ戦略において重要な役割を担っています。AIによって、従来の人力中心の対応から、効率性と精度を兼ね備えた自動化システムへの転換が実現されています。
現代のセキュリティ環境では、日々膨大な数のアラートが生成されますが、その多くが実際の脅威ではない偽警報である場合も少なくありません。AIシステムは、大量アラートを高速で分析し、真の脅威と誤検知を区別できます。セキュリティ担当者は本当に重要な案件に集中できるようになり、業務負荷の大幅な軽減が実現されます。
さらに注目すべきは、脅威検知から対応実行までの完全自動化機能です。AIシステムが実際の攻撃を検知した瞬間に、予め設定された対応手順に従って自動的に防御措置を実行します。迅速な初期対応により、攻撃による被害範囲を最小限に抑え、組織の重要資産を効果的に保護します。
AIのリスクを正しく理解し、安全な活用を
今回の記事では、AIセキュリティ対策を解説しました。AIセキュリティには、「守り」と「攻め」の2つの重要な視点があります。
「守り」の視点であるSecurity for AIは、AI技術そのものを安全に活用するための取り組みです。一方、「攻め」の視点であるAI for Securityは、高度化するサイバー脅威に対抗するためにAI技術を積極的に活用するアプローチです。AI for Securityでは、従来の人的作業では困難だった潜在的な攻撃ルートの予測や分析を可能にします。
AI活用に潜むリスクを理解し、AIを考慮したセキュリティ対策を講じていくとともに、適切に活用していくことが求められます。
ラックが提供するAI関連サービス
今回の記事では「AIによるセキュリティ対策」について解説してきましたが、AIの可能性はそれにとどまりません。近年は、業務効率化や営業活動の高度化、生成AIを活用した新たなサービス展開など、幅広い領域でAIの導入が進んでいます。最後に、ラックが提供するAI関連サービスを紹介します。
- 生成AIのセキュアな活用をサポートする「生成AI活用支援サービス」
- セキュリティの専門家が攻撃者の視点で、生成AIシステムの脆弱性を発見する「生成AI活用システム リスク診断」
- AI技術を駆使した高精度な不正取引検知で金融被害発生を防止する「AI不正取引検知サービス:AIゼロフラウド」
- 営業活動を効率化する「営業×生成AIソリューション」
生成AIのセキュアな活用をサポートする「生成AI活用支援サービス」
多くの企業がAI技術に期待を寄せる一方で、実際の導入段階では「何から始めれば良いか分からない」「セキュリティリスクが不安」「導入による効果がイメージできない」などの根本的な課題に直面しがちです。
特に生成AIは汎用性が高い反面、適切な活用方法や安全な運用ノウハウがなければ、期待した成果を得られません。
生成AI活用支援サービスは、ラック社内での活用経験を基に、スムーズな開発やセキュアな利用方法を提案します。単純なチャットボット機能に留まらず、業務プロセス全体の効率化やデータ分析の高度化など、企業の具体的な課題解決に直結する活用方法を提案できるサービスです。
社内外での豊富な開発経験をもつラックのエンジニアによる支援により、企業は試行錯誤の時間とコストを大幅に削減できます。さらに、プロトタイプ開発からリリースまでの一貫したサポートにより、企業はAI導入の不確実性を最小化しながら、確実な業務改善効果を実現できます。
セキュリティの専門家が攻撃者の視点で、生成AIシステムの脆弱性を発見する「生成AI活用システム リスク診断」
生成AI活用システム リスク診断は、攻撃者の視点から対話型AI機能を組み込んだシステムを診断し、特有のセキュリティ問題や悪用が想定されるリスクを特定します。
従来のシステム診断では発見できない、AI特有の新たな脅威が急速に拡大している現状において、未知のリスクを抱えたままAI技術を導入することはリスクを伴います。生成AIシステムは、攻撃者の不正な入力によって悪用される脆弱性を持っており、セキュリティ上のリスクを事前に把握しなければ、運用開始後に深刻な被害を受ける可能性があります。
生成AI活用システム リスク診断の強みは、攻撃者の視点を取り入れた専門的な診断により、企業が気づいていない潜在的なリスクを可視化することです。
対話型AIを入出力のインターフェースとして、自社サービスに組み込む際に発生する「AIにより重要情報が漏えいしないか」、「高度化したAIに対する攻撃手法に対応できているか」といった不安を、専門家が第三者診断を実施することで解決します。
また、「社内利用のみ」、「不特定多数に公開前提」といったそれぞれの利用環境に応じたカスタマイズされたリスク分析により、自社の状況に最適化されたセキュリティ対策を講じられます。
AI技術を駆使した高精度な不正取引検知で金融被害発生を防止する「AI不正取引検知サービス:AIゼロフラウド」
フィッシング詐欺などの「なりすまし」による不正ログインによって、インターネットバンキングやECサイトでの不正取引・金融犯罪は後を絶ちません。
これらの金融犯罪に対して、AI不正取引検知サービス「AIゼロフラウド(AI ZeroFraud)」は、AI技術を駆使することで高精度に不正取引や不正口座を検知し、被害発生を防止します。
これまでに3種類のAIエンジンを開発し、それらを組み合わせて活用することで、多角的に金融犯罪被害を抑止する仕組みを実現しています。
営業活動を効率化する「営業×生成AIソリューション」
多くの企業では営業担当者が顧客対応や提案活動以外にも提案前準備や商談後の記録や報告などの作業に時間が割かれること、営業活動が属人化しお客様の状況や提案ノウハウといった貴重な資産が共有されず非効率的な活動になっていることなどが課題として多く見られます。
これらの営業現場の課題に対して、商談スキル向上のトレーニングと営業活動で蓄積された貴重な情報資産の活用の両面で営業変革を推進できるよう、「営業×生成AIソリューション」として提供しています。お客様の情報の取り扱いにも配慮し、生成AIを安心して利用しながら、営業活動の課題解決と営業部門のレベルアップを実現します。
参考情報
※1 今後重点的に取り組むべき研究開発課題について|サイバーセキュリティタスクフォース事務局
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- もっと見る +
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR