-
タグ
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR
生成AIの活用が企業で急速に広がる中、関連情報を外部データベースから検索し、より正確で信頼性の高い回答を実現するRAG(検索拡張生成)技術が注目を集めています。
本記事では、RAGの基本的な仕組みから導入メリット、ファインチューニングとの違いを詳しく解説し、導入時の注意点やコスト面での考慮事項を紹介します。
RAG(検索拡張生成)とは?生成AIの性能を高める技術
RAG(検索拡張生成)とは、Retrieval Augmented Generationの略で、生成AIに外部の知識を与えることで、回答の精度を高める技術です。生成AIの性能を高める技術として、より正確で信頼性の高い回答の実現が期待されています。RAGは検索機能と生成機能を組み合わせた仕組みによって、従来の大規模言語モデル(Large Language Models:以下、LLM)では解決できなかった情報の古さや専門知識の不足といった課題に対処します。
現代のAI活用において、なぜ今RAGが必要とされるのか、背景と重要性について解説します。
LLMだけでは解決できない課題
LLMとは、インターネット上に公開されている大量のテキストデータから、文章の構造や意味を抽出して学習した情報のかたまりです。LLMは人間との自然な会話を実現する優れた技術ですが、学習済みの情報しか扱えないという課題があります。この制約により、最新情報への対応が困難で、新たな学習には相当な時間とコストが必要です。
さらに、社内規定や機密文書などクローズドな情報は、セキュリティ上の理由から学習データに含められません。ChatGPTなどの代表的なLLMでも、ハルシネーションと呼ばれるもっともらしい虚偽情報の生成、情報の古さ、専門的知識の不足といった課題が顕在化しています。
例えば「2030年4月からの新しい人事制度について教えて」のような質問に対しては、学習データに含まれていない情報のため適切な回答ができません。LLMが抱える構造的な問題を解決する手段として、RAG技術が注目されており、専門文書を読み込ませることで最新かつ正確な情報に基づいた回答が実現可能です。
なぜ今RAGが必要とされるのか
RAG技術が必要とされる背景には、LLMが抱える課題があります。最も重要な課題は、事実に基づかない回答を生成するハルシネーション現象で、ビジネス現場での信頼性を大きく損なう要因となりかねません。
ハルシネーションの問題を解決するためには、信頼性の高いデータベースや情報源から適切な情報を検索し、情報を基に回答を生成するRAGの仕組みが有効です。RAGの動作原理は「オープンブック試験」に例えられます。
従来のLLMが記憶のみに依存した「暗記試験」だったのに対し、RAGは必要な情報を参照しながら回答を生成する「教科書持ち込み可能な試験」のような仕組みを実現します。
RAGの特性により、推測や不確実な記憶に頼ることなく、確実な情報源に基づいた正確で信頼性の高い回答が可能となることが必要とされている要因です。
RAGは「検索」と「生成」を組み合わせた仕組み
RAGは、大規模言語モデルに検索機能を融合させた画期的なAI技術です。RAGは、質問に対して関連する情報を検索し、検索結果を基盤として正確な回答を生成する仕組みを採用しています。
従来の生成AIは、新しい知識を追加するために専用データの準備と長期間の学習プロセスが必要でしたが、RAGは質問を受けるたびに外部情報を検索し、コンテキストに取り込み、リアルタイムで最新情報に基づいた高精度な応答を実現します。
検索と生成を組み合わせたアプローチにより、企業における様々な業務効率化が促進され、AI活用の可能性を飛躍的に拡大することができる技術です。
RAGの仕組みを分かりやすく解説
RAGの仕組みは次のステップで構成されます。
- 1.ユーザからの質問を受け付ける
- 2.外部データベースから関連情報を検索する
- 3.検索情報と質問をLLMに渡し回答を生成する
それぞれのステップ別に詳しく解説します。
ステップ1:ユーザからの質問を受け付ける
RAGの最初のステップは、ユーザからの質問やリクエストを受け付ける段階です。この段階では、ユーザがチャットインターフェースや専用のフォームを通じて、AIに対する質問や指示をプロンプトとして入力します。
プロンプトは、次のステップとなる検索および回答生成プロセスの起点となる重要な要素で、ユーザの意図や求める情報の内容を正確に把握するための基礎です。入力された質問は、単なるテキストデータとしてではなく、AIが理解可能な形式に変換され、次の検索ステップへと引き継がれます。
ステップ2:外部データベースから関連情報を検索する
RAGの第2ステップでは、受け付けた質問に対して外部データベースから関連する情報を検索する重要なプロセスが実行されます。この検索フェーズでは、LLMが持っていない知識を補完するため、企業内に蓄積された社内情報や外部の最新データといった多様な情報源から、質問内容に最も関連性の高い文書や資料を特定します。
システムは、質問の内容を分析し、膨大なデータの中から適切な情報を効率的に抽出する作業が必要です。検索フェーズの実装においては、外部データをどのように構造化するか、検索しやすい形式に文章を数値で表現するベクトル化手法、そして検索システムの選択が極めて重要です。
目的に応じた最適な検索手法の選定が、RAGシステム全体の性能を大きく左右します。
ステップ3:検索情報と質問をLLMに渡し回答を生成する
RAGの最終ステップでは、検索で得られた関連情報とユーザの質問を組み合わせてLLMに送信し、最適な回答を生成します。この回答フェーズでは、単純にユーザの質問だけをLLMに投げるのではなく、検索フェーズで取得した関連文書の情報を背景や参考資料として付け加えて送信することが特徴です。
LLMは、受け取った豊富なコンテキスト情報を基盤として、質問に対してより正確で具体的な回答を生成できます。従来のLLMが学習済みの知識のみに依存していたのに対し、RAGではリアルタイムで取得した最新の関連情報を活用することで、事実に基づいた信頼性の高い回答を実現します。
RAGを導入する4つのメリット

RAGの導入は、従来のAIシステムが抱えていた様々な課題を解決し、企業のAI活用を大幅に向上させる効果をもたらします。特に注目すべきは、ハルシネーションと呼ばれる虚偽回答の抑制、社内情報などの専門知識への対応、最新情報の反映、そして回答の根拠となる情報源の明示など4つの重要なメリットです。
RAGを導入する4つのメリットを解説します。
メリット1:ハルシネーション(嘘の回答)を抑制する
RAGの最大のメリットは、生成AIが作り出すハルシネーションと呼ばれる虚偽回答を効果的に抑制することです。ChatGPTなどのLLM単体では、学習データの古さや不足が原因で事実とは異なる回答を生成してしまうケースが頻発します。
例えば、一般的なLLMに「最新の法改正内容を教えて」と尋ねても、学習時点にその情報が含まれていない場合、AIが推測で答えてしまい、誤った内容を生成してしまうことがあります。一方、RAGを活用すれば、最新の法令データや公式発表などを参照したうえで回答を生成できるため、このような誤答(ハルシネーション)を大幅に抑制できます。
RAGでは学習済みデータに依存することなく、質問に関連する信頼できる外部情報を検索し、その情報を基盤として回答を生成するため、回答の根拠が明確です。
この仕組みにより、推測や不確実な記憶に頼ることなく、確実な情報源に基づいた信頼性の高い回答が実現され、ビジネス現場での実用性が向上します。
メリット2:社内情報など専門的な回答が可能になる
RAGのメリットとして、社内情報や専門的な知識に基づいた回答が可能になることが挙げられます。通常の生成AIは、主にインターネット上で公開されている既存情報を学習データとして活用するため、企業の機密情報や非公開データを扱えません。
一方、RAGシステムでは、作業マニュアルや顧客情報、社内規定といった組織特有の専門情報をデータベースに登録することで、これらの情報を基盤とした具体的で実用的な回答が生成可能です。そのため、従来は人から人へと口頭で伝承されていた貴重なノウハウや、文書化されているものの活用しきれていなかった社内知識を効果的に活用できるようになります。
社内情報を基にした専用の生成AIが実現すれば、蓄積された組織の知識やノウハウを組織全体で共有し、業務プロセスの大幅な効率化と生産性向上が期待できます。
メリット3:最新の情報を反映した回答ができる
RAGのメリットの1つが、最新情報を即座に反映した回答が可能になることです。従来のLLMでは、学習データの更新に長時間を要し、リアルタイムな情報への対応が困難でした。
RAGシステムでは、参照するデータベースが最新の状態に保たれていれば、常に現在の状況に即した正確な情報を基にした回答を生成できます。この特性により、市場動向や法改正、企業の最新方針など、頻繁に変化する情報も、タイムラグなく対応可能です。
さらに、RAGでは事前の学習プロセスが不要で、その時々の状況に応じて必要な情報をデータベースに追加するだけで済むため、情報更新の負担も大幅に軽減されます。
メリット4:回答の根拠となる情報源を提示できる
RAGの4つ目のメリットは、回答の根拠となる情報源を明確に提示できることです。LLMでは、どの情報を基に回答を生成したのかが不明瞭で、生成された情報の信頼性を検証することが困難でした。
RAGシステムでは、ユーザの質問に対して検索で取得した具体的な情報を根拠として活用するため、回答の信頼性が向上します。さらに、ユーザは回答の妥当性を自ら確認でき、必要に応じて元の情報源にアクセスして詳細を調べられます。
特にビジネスの現場では、重要な判断を下すケースが多いため、説明責任の確保は極めて重要です。RAGによる情報源の明示機能は、AI活用における透明性と説明責任を両立させ、組織内での信頼性の高いAI導入を実現する基盤となり得る要素です。
RAG導入で注意すべき3つのデメリット
RAG導入の際は次の3つのデメリットに注意しなければなりません。
- 1.検索精度が回答の質を左右する
- 2.導入と運用に専門知識とコストが必要になる
- 3.情報漏えいのリスク管理が必須になる
それぞれのポイントを解説します。
デメリット1:検索精度が回答の質を左右する
RAGのデメリットとして、検索精度が回答の質を左右することが挙げられます。RAGシステムは外部の情報源から関連データを検索して回答を生成する仕組みのため、組み込まれた文書やデータベース自体に誤りがある場合、誤った情報を基にした回答が出力されます。
RAGの性能は参照する情報源の品質に依存しており、「ゴミを入れればゴミが出る」という状況が発生しかねません。問題を防ぐためには、データベースに登録する情報の事前チェックが不可欠で、外部情報のファクトチェックや信頼性の検証を徹底する必要があります。
さらに、情報は時間の経過とともに変化するため、定期的なメンテナンスを行い、古い情報の更新や削除の継続的な実施が必要です。メンテナンスの運用管理を怠ると、RAGシステム全体の信頼性が損なわれ、かえって誤情報の拡散につながるリスクがあります。
デメリット2:導入と運用に専門知識とコストが必要になる
RAGのデメリットの1つが、導入と運用において専門知識とコストが必要になることです。RAGシステムの構築には、検索コンポーネントと生成コンポーネントの異なる技術要素を効果的に組み合わせる必要があり、設計と実装には高度な専門的知識が求められます。
深層学習の基礎となる技術のTransformerをベースとした生成モデルの統合や調整作業は複雑で、AIや機械学習に関する深い理解なしには適切に実行できません。また、システムの最適化作業も継続的に必要となり、検索精度の向上やレスポンス速度の改善などには専門的な技術が不可欠です。
生成AIの特性や限界を十分に理解していなければ、RAGシステムを自在に活用することは困難で、期待した効果を得られません。導入時の初期投資だけでなく、継続的な運用コストや専門人材の確保が必要となり、組織にとって大きな負担となる可能性があります。
デメリット3:情報漏えいのリスク管理が必須になる
RAGのデメリットとして、情報漏えいのリスク管理が必須になることが挙げられます。RAGは、企業の様々な情報をデータベースに登録して活用しますが、その中に秘匿性の高い企業情報や機密データが含まれている場合でも、生成AIはそれらの情報を回答に使用して良いかの適切な判断ができません。
そのため、ユーザからの質問に対して、意図せずに機密情報を含んだ回答を生成してしまい、重要な企業情報が流出するリスクが存在します。特に、複数の部門や外部パートナーがシステムにアクセスする環境では、リスクはさらに高まります。
情報漏えいを防ぐためには、データベースへの登録時における情報の厳格な選別、暗号化技術の導入、ユーザごとのアクセス権限制限などのセキュリティ対策が必要です。
RAGとファインチューニングとの違いは?
RAGとファインチューニングは、いずれも生成AIの性能向上を目指す技術ですが、そのアプローチと特性には大きな違いがあります。
具体的な違いは次の通りです。
| 比較項目 | RAG(検索拡張生成) | ファインチューニング |
|---|---|---|
| 主な目的 | 外部の最新・専門知識をAIに与え、回答の正確性を高める | AIの応答スタイルや振る舞いを特定のタスクに合わせて調整する |
| 得意なこと | ・ハルシネーションの抑制 ・社内文書など独自データの活用 ・回答の根拠となる情報源の提示 |
・特定の口調やブランドイメージの再現 ・特定の対話形式への最適化 ・専門用語の学習 |
| 知識の更新 | 容易 (データベースの情報を更新するだけ) |
困難 (モデルの再学習が必要) |
| 導入コスト | 比較的低い (主にデータベース利用料) |
高い (大量の教師データと学習コスト) |
| 導入期間 | 比較的短い | 長い |
| 適した例 | 最新の社内規定に基づくチャットボット | 特定のキャラクターを演じるAI |
RAGとファインチューニングとの違いについて詳しく解説します。
知識の与え方の違い
RAGとファインチューニングの基本的な違いは、AIモデルに知識を与える手法にあります。RAGは、必要なときに参考書を開いて調べながら答えを作るような仕組みです。一方、ファインチューニングは、すでに学習済みのAIモデルに対して新しいデータを追加で学習させる方法で、AIに特定の本を丸暗記させ、記憶した知識を元に回答させるイメージに近い手法です。
RAGが外部情報への依存型アプローチであるのに対し、ファインチューニングは内部知識の蓄積型アプローチという根本的な違いがあります。AIに対する知識の与え方の違いにより、それぞれの技術には異なる利点と制約が生まれ、適用場面や期待できる効果も大きく変わります。
得意なタスクと不得意なタスクの違い
RAGは、広範囲にわたる知識が必要なケースや、迅速な情報提供が求められる状況で特に効果を発揮します。例えば、社内情報回答チャットボットでRAGを実装し、社内FAQシステムと生成AIを連携させることで、膨大な社内情報から適切な回答の提供が可能です。
一方、ファインチューニングは、特定の業界や専門分野、企業固有のニーズに深く特化した応答を提供する際に有効な手法です。医療や法律といった高度な専門知識が必要な領域や、企業独自のカスタマーサポート対応、多言語対応のチャットボットなどで最適な性能を発揮します。
RAGが情報の幅広さと即時性を重視するのに対し、ファインチューニングは特定領域における深い理解と一貫性のある応答を重視する違いがあり、目的に応じた適切な選択が重要です。
コストと更新の容易さの違い
RAGとファインチューニングには、コストと更新の容易さにおいても違いがあります。一般的に、RAGの方がファインチューニングよりもコストが低いとされています。
ファインチューニングでは高品質なデータセットの準備と前処理、さらに高性能なハードウェアを必要とするため、特に初期の再学習時に高額なコストが発生する傾向があります。一方、RAGの開発コストは、主にデータ検索システムのインフラ設計やデータ整備が大きな割合を占めており、初期費用を比較的抑えて構築できます。
更新の容易さの観点では、RAGは新しい情報をデータベースに追加するだけで即座に反映できるのに対し、ファインチューニングは新しいデータで再学習を行う必要があり、時間とコストの両面で負担が大きくなることが特徴です。
RAGの具体的な活用事例
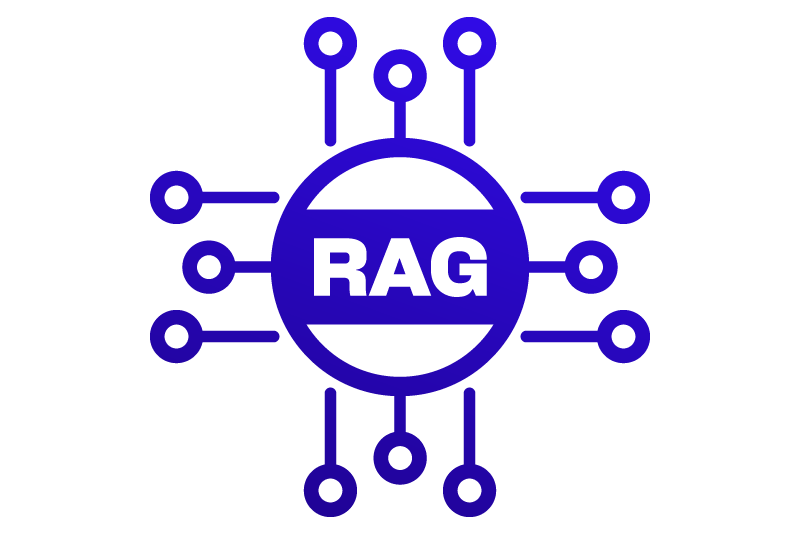
RAGの具体的な活用事例を2つ紹介します。RAGを活用してどのように課題を解決したのか、自社の取り組みの参考にしてみてください。
業務効率化支援ツールを本格導入
ある大手企業では、全従業員を対象とした業務効率化支援ツールの本格運用を開始しています。このシステムは、RAG技術を核とした生成AIシステムで、チャット形式での業務支援を実現しています。
システムの特徴は、同社が長年にわたって蓄積してきたナレッジデータや業務マニュアル、社内FAQなど多様な情報資源を活用し、従業員の質問に対して適切な情報を検索して自然な回答を提供することです。
大規模言語モデルと社内データの連携により、従来は人に聞かなければわからなかった業務上の疑問も、AIとの対話を通じて迅速に解決できるようになりました。全社展開に至る前には、限定的な部門でのトライアル運用を実施し、システムの有効性と実用性を十分に検証しています。
この取り組みにより、情報アクセスの効率化と業務プロセスの改善が実現され、組織全体の生産性向上に貢献している先進的な事例です。
RAGを活用した社内ChatGPTによる業務効率化
株式会社横浜銀行と株式会社東日本銀行では、従業員の業務効率化と生産性向上を目的として、2023年11月に「行内ChatGPT」の導入を発表しました。システムの構築は、ラックのAI開発チームの支援を受け、ラックが社内向けに提供している生成AIサービス「LACGAI」を基盤として活用しました。
開発過程で明らかになったのは、インターネットで公開されている一般的な情報だけでは期待した結果を得られず、銀行業務特有の専門知識や社内文書を効果的に学習させることの重要性でした。
そこで、銀行内の業務文書を活用して的確な回答を生成するため、RAG技術が鍵となる要素として導入されています。システム開発および運用においては、金融機関として極めて重要なセキュリティ上の課題を最優先に検討し、将来的には生成AIツールの連携を強化することで、日常業務の抜本的な改革と生産性向上を実現することを目指しています。
RAGの精度を高めるためのポイント
RAGの精度を高めるためのポイントとして、次の要素が挙げられます。
- 目的に合わせた検索方法の選定
- 検索しやすいデータ形式への前処理
- 最適な回答を引き出すプロンプトの設計
どのようなことに注意すべきかを解説します。
目的に合わせた検索方法の選定
RAGの精度を高めるためのポイントとして、目的に合わせた検索方法の適切な選定があります。RAGが大量のデータから情報を抽出する際には、次の3つの検索手法から最適なものを選択することが求められます。
| 検索手法 | 特徴 |
|---|---|
| 全文検索 | ユーザの質問に含まれるキーワードに着目し、データベースからそのキーワードを含む文章を直接的に抽出する |
| ベクトル検索 | ユーザの質問と検索対象データをベクトル(数値で表現した形式)に変換し、意味的な類似度が高い情報を探し出す |
| ハイブリッド検索 | 全文検索とベクトル検索の両方の利点を組み合わせた手法 |
利用目的や扱うデータの特性を考慮して、これらの検索手法を適切に選定することがRAGの性能向上に直結します。
検索しやすいデータ形式への前処理
RAGの精度向上において、検索しやすいデータ形式への前処理も重要なポイントです。前処理とは、不ぞろいで扱いにくいデータをAIにとって処理しやすい形に加工するプロセスで、RAGの実装において重要な工程の1つとされています。
具体的な前処理の手法として、次の要素があります。
| 前処理の手法 | 特徴 |
|---|---|
| データクレンジング | 情報に混入したエラーやノイズ、不完全な部分を取り除く |
| 正規化 | 異なる形式や単位で記録されたデータを統一された基準に合わせる |
| エンベディング | 文章の意味や文脈を数値形式で表現 |
| アノテーション | 各データに適切な説明や分類タグを付与 |
前処理を適切に実施することで、データベースに格納されるデータの質が向上し、結果としてRAGシステム全体の検索精度と回答品質が改善されます。
最適な回答を引き出すプロンプトの設計
RAGの精度向上には、最適な回答を引き出すプロンプトの戦略的な設計が不可欠です。効果的なプロンプトを構築するためには、単純な質問文だけでなく、構成要素を体系的に検討する必要があります。
AIの応答品質を向上させるためには、基本的な命令や指示に加えて、背景となる情報や状況説明など補完的な文脈を適切に組み込むことが重要です。さらに高い精度を実現するには、具体的な応答形式の指定や詳細な条件設定、期待する回答の範囲や深度などを明確に示すことで、AIの理解を深められます。
プロンプトエンジニアリングと呼ばれる専門技術は、RAGシステムから期待通りの高品質な回答を得るための重要なスキルです。適切に設計されたプロンプトは、検索される情報の関連性を高め、生成される回答の正確性と有用性を改善する効果をもたらします。
さいごに
本記事では、生成AIの性能を飛躍的に向上させるRAG技術について、仕組みから導入メリット、具体的な活用事例まで幅広く解説しました。
RAGは外部データベースから関連情報を検索し、それを基盤として正確な回答を生成する革新的な技術です。ハルシネーションの抑制、社内情報の活用、最新情報の反映、情報源の明示といった4つの主要メリットにより、企業でのAI活用をより実用的なレベルに押し上げます。
ラックでは、生成AIを活用するための環境を、セキュアかつ効率的に構築できるソリューションや生成AIを様々なシーンで活用し、企業の業務効率化を総合的に支援する様々なサービスを提供しています。
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- もっと見る +
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR























