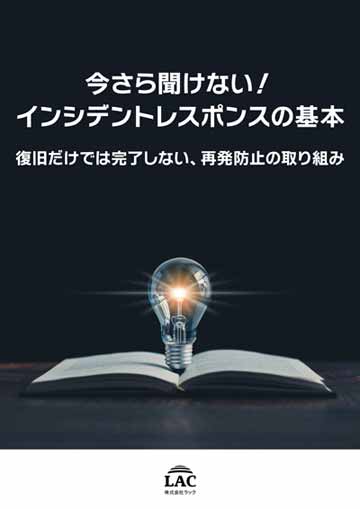-
タグ
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR
インシデントレスポンスの強化は、企業にとって避けられない重要な要素です。インシデントレスポンス能力が低い企業は、セキュリティインシデントによる被害のリスクが常にあり、発生時に適切な対処ができず二次被害が広がる懸念があります。
今回の記事では、インシデントレスポンスを強化するための企業が押さえるべき基本と実践ポイントを解説します。また、インシデントレスポンスの各手順も紹介します。
インシデントレスポンスとは何か?
インシデントレスポンスとは、サイバー攻撃などに遭遇した際に、適切な対応を取ることで被害を最小限に抑え、迅速な復旧を目指すための対応や体制構築を指します。まずはインシデントレスポンスの目的や今必要とされている背景を解説します。
インシデントレスポンスの目的
セキュリティインシデントとは、組織において意図的に引き起こされたセキュリティ上の出来事や事象のことです。サイバーセキュリティの領域においてのインシデントの概念は、偶発的なアクシデントやハプニングとは明確に区別され、悪意ある第三者による計画的な攻撃への対処に焦点を当てています。インシデントレスポンスとは、インシデントに対する対応プロセスです。
インシデントレスポンス対象の具体例としては、マルウェア感染や不正アクセスなどの外部からのサイバー攻撃が代表例として挙げられます。サイバー攻撃は組織の情報資産や業務継続性に深刻な影響を与える可能性があるため、迅速かつ適切な初動対応が極めて重要です。
インシデントレスポンスの目的は、セキュリティインシデントが発生した際に組織が被る損害を最小限に抑え、迅速に侵害を除去することです。早期発見と適切な封じ込め措置により、被害の拡大を防ぎ、事業への影響を軽減します。
また、証拠保全や原因分析を通じて再発防止策を講じることで、組織のセキュリティ体制全体の強化にも寄与します。
なぜ今インシデントレスポンスが重要なのか
インシデントレスポンスが重要視される背景には、サイバー攻撃の変化があります。攻撃者の手法は年々高度化・巧妙化しており、従来の防御策だけでは完全に防ぎきれない状況です。
企業が直面する脅威は多様化し、影響も深刻化しています。ランサムウェア攻撃による業務停止は事業継続性を直接脅かし、サプライチェーン攻撃は取引先企業にまで被害が波及する可能性があります。
また、個人情報漏えい事件は法的制裁や損害賠償請求に加え、長期的なブランドイメージの毀損という回復困難な損失となりかねません。
このような環境下で、平時から適切なインシデントレスポンス体制を整えておくことは組織の生存戦略として不可欠です。事前の準備があるからこそ、インシデント発生時に迅速かつ効果的な対応が可能となり、被害を最小限に抑制し、事業の早期復旧につながります。
インシデントレスポンス体制構築の要点
インシデントレスポンスは、事前の計画と体制整備が不可欠です。インシデントレスポンス体制構築におけるポイントは次の通りです。
- CSIRTの役割と組織内での位置づけ
- インシデント対応に必要なスキルと人材育成
- インシデントレスポンス(IR)計画の策定
それぞれの要点を詳しくみていきましょう。
CSIRTの役割と組織内での位置づけ
インシデントレスポンス体制を強化する手段の1つとして、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)と呼ばれる専門チームを設置することがあります。CSIRTは、組織でセキュリティインシデントへの対応を主導する中核的な役割を担うことが多く、インシデントレスポンス体制の中で重要な機能を果たします。
CSIRTの機能は2つの重要な側面から構成されます。第一に「消火活動」としての事後対応があり、インシデント発生時の迅速な封じ込めや復旧作業が役割です。第二に「防火活動」としての事前対応は、平時からの情報収集、脅威分析、セキュリティ意識向上のための啓蒙活動を継続的に実施します。
効果的なCSIRT構築においては、事故はいつか起きるという現実的な前提に立つことが重要です。社内各部門との横断的連携体制を確立し、さらには社外の専門機関や同業他社との協力関係を築くことで、包括的な対応能力を獲得できます。
インシデント対応に必要なスキルと人材育成
インシデント対応における人材育成は、高度な専門技術をもつセキュリティアナリストの確保と育成が重要課題です。代表的な専門職として、マルウェアアナリストとフォレンジックアナリストが挙げられ、これらの専門家がインシデント調査の中心を担います。
マルウェアアナリストやフォレンジックアナリストは、報告されたセキュリティインシデントに対して詳細な分析を実施します。マルウェア検体の挙動解析、デジタルフォレンジック調査、ログ分析などを通じて攻撃の全容を解明し、被害組織に対する具体的な復旧支援とセキュリティ強化策を提案することが役割です。
また、トリアージ担当者は、インシデント発生時に迅速に情報を整理し、優先順位を付けて適切な対応へと誘導します。発生したインシデントの深刻度や対応の緊急性を総合的に評価し、限られたリソースを適切に配分するのが主な役割です。
ラックでは、従業員向けにインシデントレスポンスのセキュリティ講習を開催しています。一般社員、職員レベルや期間に応じた講習を用意しています。
| コース名 | 内容 | 講習時間 |
|---|---|---|
| インシデントレスポンス概論 | 『情報セキュリティ事故対応1日コース 机上演習編』の座学部分をオンライン用にカスタマイズしたコース | 60分 |
| 情報セキュリティ事故対応1日コース 机上演習編 | インシデントレスポンスを机上環境で体験できる | 1日 |
| 情報セキュリティ事故対応2日コース 実機演習編 | インシデントレスポンスを実機環境で体験できる | 2日 |
インシデントレスポンス計画の策定
インシデントレスポンス計画(以下、IR計画)は、組織がサイバー攻撃に直面した際の対応準備を文書化した指針です。IR計画書により、混乱しがちな緊急時でも組織全体が統一された手順で効果的な対応を実現できます。
IR計画によって、IR対応の責任者の設定や連絡体制の確立、技術的対処手順、外部機関との連携方法など、詳細な行動指針をあらかじめ策定することで、実際のインシデント発生時の判断遅れや対応ミスを防止できます。また、法的要件や規制遵守も事前に整理し、適切な報告義務を果たせるよう準備できることもメリットです。
IR計画の策定において重要なのは、計画の継続的改善です。インシデント対応完了後には必ず振り返り会議を実施し、対応フローの妥当性、復旧作業の効率性、再発防止策の有効性を客観的に評価します。
インシデントレスポンスの主要な対応フェーズ
インシデントレスポンスは、次の5つのフェーズで策定されます。
- 1.準備
- 2.発生:検知・分析
- 3.初動対応:封じ込め・根絶・復旧
- 4.復旧作業:インシデント後の対応
- 5.再発防止
インシデントレスポンスの全体像や各フェーズで実施する内容は「今さら聞けない!インシデントレスポンスの基本」と題したホワイトペーパーにて詳細に解説しています。
インシデントレスポンス体制をこれから構築しようとする組織に向けて、IR計画を作成する際に検討すべき項目や注意すべきポイント、役割分担と関係者間の連携などを紹介します。
今さら聞けない!インシデントレスポンスの基本
ダウンロード
インシデント発生時の初動対応と連携

インシデント発生時は初動対応が何よりも大切です。関係者と即連絡を取り、適切な対処を行うことで被害を最小限に抑えなければなりません。
インシデント発生時の初動対応と連携でポイントとなる要素を詳しくみていきましょう。
発生時に行うべき最優先事項とは
インシデント発生時の最優先事項は、被害の拡大阻止と適切な初動対応の実施です。初動対応の段階では冷静かつ迅速な判断が組織全体の被害規模を決定するため、事前に策定された手順に従った組織的対応が求められます。
まずは発生事象と影響範囲の特定です。同時に、CSIRTなどの専門対応チームが中心となり、詳細調査や法的対応に備えて、関連するログデータやシステムイメージの証拠保全を実施します。
収集した情報を基に、今回の事象がセキュリティインシデントに該当するか否か、該当する場合の緊急度レベルを客観的に判定します。初期トリアージにより、限られた対応リソースを効果的に配分し、影響を最小限に抑制できる適切な対応戦略を決定します。
関係各所への適切な報告と情報共有
インシデント発生時は、適切なタイミングと方法での情報開示により、ステークホルダーとの信頼関係を保持しながら、協力的な対応体制を構築しなければなりません。
社内では各部署と経営層への迅速な状況共有により組織的対応を調整し、社外では顧客や取引先、監督官庁など、関係機関への適切な通知を行います。特に個人情報漏えいなどの二次被害が想定される場合は、被害者本人への直接報告が法的・倫理的義務です。
大規模インシデントや社会的影響が広範囲に及ぶ場合は、公式Webサイトやメディアを通じての公表が必要です。併せて問い合わせ窓口を設置し、関係者からの質問や不安に迅速に対応することで、混乱の拡大を防ぎましょう。
専門組織への相談と支援要請の判断
自社リソースだけでは解決困難な高度な技術的課題や、法的対応が必要な複雑なインシデントにおいて、専門組織との連携は被害最小化と適切な問題解決のために重要です。
支援要請先としては、IT製品メーカーや保守ベンダからは技術的な解決策と復旧支援を、公的機関の相談窓口からは法的助言と情報共有による同種被害の防止支援を受けられます。※1また、業界団体や専門コンサルティング会社からは、類似事例の知見や最新の脅威情報を得られます。
将来的な訴訟対応を見越した証拠保全とフォレンジック調査の実施も重要なポイントです。法的責任の明確化、損害賠償請求への対応、規制当局への報告義務履行などにおいて、専門的なデジタルフォレンジック技術による客観的事実の確定が欠かせません。
インシデントレスポンス能力向上のために

インシデント発生時は初動対応が何よりも大切です。関係者と即連絡を取り、適切な対処を行うことで被害を最小限に抑えなければなりません。
インシデント発生時の初動対応と連携でポイントとなる要素を詳しくみていきましょう。
インシデントレスポンス能力向上のためには、定期的な訓練とインシデント対応計画の見直しが必要です。最新のサイバー脅威情報の継続的な収集は常に必要であり、可能であれば外部専門サービスの活用も選択肢に入れるべきでしょう。
インシデントレスポンス能力向上は、組織の安定した運営には欠かせません。インシデントレスポンス能力向上のために必要な要素を解説します。
定期的な訓練とインシデント対応計画の見直し
インシデントレスポンス能力の向上には、定期的な訓練実施が必要であり、定期的な訓練によって実際のインシデント発生時における対応品質と効率性が改善されます。
定期訓練のインシデント報告書には発生原因の詳細分析、実施した対応策、復旧作業の経過記録、将来的な再発防止策などが記載され、これらの文書化能力は訓練を通じて段階的に習得可能です。適切な報告書作成により、事後検証の精度向上が実現されます。
また、効果的なインシデントレスポンスを維持するためには、セキュリティポリシーやルールの定期的な見直しも不可欠です。新たな脅威動向、技術環境の変化、組織体制の変更に対応して、既存の手順書や対応計画を適切に更新しなければなりません。
訓練やシミュレーションで発見された問題点を組織的にフィードバックし、次回の訓練内容や対応手順の改良に反映します。
最新のサイバー脅威情報の継続的な収集
インシデントレスポンス能力の向上において、最新のサイバー脅威情報を継続的に収集する脅威インテリジェンスの活用が必要です。
脅威インテリジェンスとは、攻撃者の手法や標的選定基準、使用ツールなどに関する情報を先行的に収集する取り組みです。収集、分析、評価、配布の各段階で組織の状況に合わせて分析することで、最新の脅威情報を組織の具体的な対策指針へと反映できます。脅威インテリジェンスの活用により、将来的な攻撃パターンの予測と事前の対策準備が可能です。
脅威インテリジェンスを基盤とした戦略策定により、組織は限られたセキュリティ予算を効果的な領域に集中投資できます。全方位的な防御ではなく、自組織に対する現実的脅威に焦点を絞った重点防護により、投資対効果が最大化されます。
また、攻撃者の戦術変化に応じた対策調整も可能となり、常に一歩先を行く防御体制の構築が実現されることもメリットです。
外部専門サービスの活用も選択肢に
インシデントレスポンス体制の効果的な構築において、外部専門サービスの活用は、現実的な制約を踏まえた実用的なアプローチです。
まず、経営層によるインシデントレスポンスの正しい理解と承認獲得が欠かせません。経営陣がサイバーセキュリティを単なるIT部門の技術課題ではなく、事業継続性に直結する戦略的経営課題として認識することで、適切な予算配分と組織的支援が確保されます。
実装段階では、利用可能な人材と予算の制約を現実的に評価し、活動範囲を最小限に絞ったスモールスタートからの構築が効果的です。全機能を自社で内製化する必要はなく、高度な技術的専門性が要求される分野や緊急時対応は、外部専門家を積極的に活用します。
外部の専門家を活用することで、限られたリソースでも実用的なインシデント対応能力を迅速に確立でき、組織の成長に応じて段階的に機能拡張を図れます。
継続的な改善でインシデントに強い組織へ
今回の記事では、インシデントレスポンスを強化するための企業が押さえるべき基本と実践ポイントを解説しました。インシデントレスポンスとは、組織において意図的に引き起こされたセキュリティ上のトラブルに対する対応プロセスです。
インシデント対応における人材育成は、高度な専門技術をもつセキュリティアナリストの確保と育成が重要課題です。専門スキルをもった人材は、インシデント分析の結果を基に将来的な脅威への対策を立案・実行できます。これにより、組織全体のセキュリティレベル向上に大きく貢献します。
インシデント対応には専門的なスキルが求められるため、外部の専門家を活用することも有効な手段です。ラックのサイバー救急センターでは、インシデント発生時の迅速な封じ込め、調査、根絶、復旧、利害関係者への報告などを支援する緊急事故対応サービス「サイバー119」を提供しています。
取引先や監督官庁への説明、メディア対応、公表後におけるSNS監視、ネガティブなコメント発見時の対応なども総合的にサポートしています。ステークホルダーへの説明、メディア対応の他、公表後におけるSNSやダークウェブなどの監視、ネガティブなコメント発見時の対応まで総合的にサポートします。マルウェアなどのウイルス感染やサイバー攻撃、Webサイト改ざん、情報漏えいなどのセキュリティインシデントの疑いや、被害などが発生したらすぐにご連絡ください。

緊急対応窓口:
サイバー救急センター
セキュリティに係るお客様の緊急事態に際し
迅速にお客様をご支援する緊急対応サービスです。
緊急事態が発生したら今すぐ「サイバー救急センター」にご相談ください。
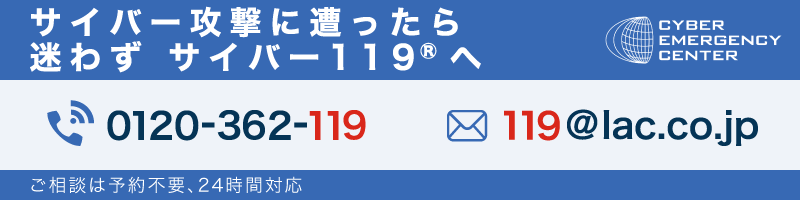
参考情報
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- もっと見る +
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR