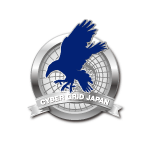-
タグ
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR
生成AIは、ビジネスだけでなく教育現場にも大きな影響を与えています。話し言葉で聞けば、どんなことでも一定の回答をくれる生成AIは、学生にとって救世主と見えてもおかしくないでしょう。教える側のメリットも計りしれません。その意味で、AI時代の教育を改めてどうあるべきか、考えるべき時が近づいているのかもしれません。
論文を書いてくれる「魔法」
2022年末の「ChatGPTショック」の後、生成AIをいち早く受け入れたのは学生だったかもしれません。若さゆえの吸収力や柔軟性で、新しいテクノロジーを使いこなすことにかけては大人を凌ぐものがあります。特に米国では、大学生が論文にChatGPTを使用したことが話題になりました。米国の教育では論文(エッセイ)を書く機会が多いと言われますが、論文作成はまさに生成AIが得意とすることの1つです。
おそらく、教授たちは対応に頭を悩ませたことでしょう。というのも、人は便利なものに抗えません。ChatGPTは公開からわずか2カ月で月間アクティブユーザー数1億人に到達し、史上最速で広まったコンシューマー向けアプリケーションとなりました。
そうこうするうちに、プリンストン大学の学生がAIで作成された論文かどうかを見抜く「GPTZero」を作成しました。その後も、AI生成の文章を検出してそれを人間らしい文体に修正することで、AI検出機能にひっかかりにくくするために使う「Undetectable AI」、オランダ発の学術論文向けオンライン校正・添削サービス「Scribbr」(スクリブール)といったツールが次々と登場し、AI Detector(AI検出ツール)という分野が生まれています。
生成AIそのものも進化を続け、ChatGPTに続きGoogle Gemini、Anthropic Claude、Perplexityなどが登場しています。テキストだけでなく、画像、動画とマルチモーダル化も進んでいます。ビジネスの現場でも、要約、翻訳、アイデア出しなど、今では当たり前のように使っているという人も多いことでしょう。生成AIが一般向けに登場してまだ3年未満と考えると、改めて世界は様変わりしたと実感します。
学生の利用率は着実に高まるが、不満も
学校は学生によるAIの使用にどう対応すべきでしょうか。古くは計算機、最近ではスマホと、新しい技術が登場すると教育現場は対応を求められてきました。そして今、生成AIとの向き合い方が問われています。
まずは学生の利用状況を見てみましょう。全国大学生活協同組合連合会の学生実態調査(2025年2月発表)※1によると、生成AIの利用経験があるという学生は68.2%、前回調査の46.7%から増えています。利用目的は「授業や研究」「論文・レポート作成の参考」「翻訳、外国語作文」が上位を占めています。
※1 第60回学生生活実態調査 概要報告|全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)
しかし、英国の調査結果を見ると、68%を少ないと感じてしまうかもしれません。高等教育の独立系シンクタンクであるHEPI(Higher Education Policy Institute)が2025年2月に発表した最新の調査では、学生の92%が生成AIを使っているという結果が出ています。2024年は66%だったというので、26ポイントもの増加となります。用途としては、「解説」「要約」「リサーチアイデア探し」がトップ3で、18%はAIが生成した文章をそのまま提出物に「コピペ」していたといいます。
また、調査では男子学生の方が生成AIの利用に前向き、女子学生は懸念を抱く傾向が強いといった男女差、所得が高い家庭の学生の方が前向きといった家庭の貧富の差、STEM履修学生の方が前向きであるなどの実態も明らかになりました。前回の調査よりも利用姿勢に差が開いていると報告しています。
一方で、学生側からは不満もあるようです。AIスキルは不可欠だと感じているものの、「大学からきちんとサポートがある」と感じている学生は36%にとどまったそうです。
英国を参照した理由の1つが、英国は2014年と早期にプログラミングを必修化したという背景があります。英国生まれのシングルボードコンピュータの「Raspberry Pi」も、教育目的で誕生したプロジェクトです。そして、英国はDeepMind(Googleが買収)などのAIスタートアップも生んでいます。
日英の政府の対応
学生が生成AIを積極的に受け入れる一方で、大学レベルでの対応も加速しています。英国ではすでに80%の教育機関が明確なAIポリシーを持ち、76%が評価課題におけるAIの使用を発見できるだろうと回答しています。いずれも、前回(2024年)の調査から増加しており、教育機関が本腰を入れてAIと向き合い始めたことがわかります。日本でも東京大学をはじめ、多くの大学がポリシーを明文化し、現場の混乱を抑える工夫を進めています。
では、政府側はどうでしょうか。英国の教育省は2025年1月、教育におけるAI利用についてのポリシーペーパー※2を発表しました。同時期に英国政府が掲げたAIの受け入れ計画「AI Opportunities Action Plan※3」(AI機会行動計画)に歩調を合わせたもので、個別最適化された指導やカリキュラム設計の効率化など、教員側にとっての利点を挙げています。
※2 Generative artificial intelligence (AI) in education - GOV.UK
※3 AI Opportunities Action Plan - GOV.UK
日本では、小学生・中学生の義務教育段階について、文部科学省が2024年に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン※4」とする指針を出しています。ここでは、「人間中心の利活用(最終判断と責任は人間にある)」、「情報活用能力の育成強化(生成AIの仕組みの理解、使いこなす力、情報モラルなどの情報活用能力の育成など)」などを基本的な考え方と定め、教員と児童それぞれの利用で考慮すべきポイントを挙げています。
※4 文部科学省 初等中等教育局「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」
また、デジタル庁は2025年6月に「教育DXロードマップ」を公表しました。生成AIについて、学校の働き方改革や学びの充実に活用する方針や施策を明記しています。
※5 デジタル庁 総務省 文部科学省 経済産業省「教育DXロードマップ」
AI時代の教育をどう設計するか
生成AIは教育現場に深く入り込み、学び方や評価の在り方に大きな変化をもたらしつつあります。日本ではガイドラインを整備しながら慎重に対応が進められ、英国では大学や政府レベルで具体的なポリシーを整備し、利用を前提としたルールづくりが加速しています。一方でエストニアは、AI Leap 2025に象徴されるように、国家として積極的にAIを教育へ取り入れ、学習者・教師双方のスキル向上を目指す先進的なモデルを提示しています。
この対比から見えるのは、「生成AIをどう活用するか」が教育の質を左右しかねない現実です。生成AIは論文作成や翻訳、リサーチ補助などで高い利便性を発揮する一方、学生の批判的思考力や独創性を損なうリスクもはらんでいます。だからこそ、教育現場には「AIを禁止するか/許可するか」という二元論ではなく、AIの力を前提に、学びの設計を根本から再構築する視点が求められます。
例えば、論文という形式そのものの意義を問い直し、AIの出力を評価・検証するスキルや、AIを使いこなす情報リテラシーの育成を重視するといった方向があるでしょう。さらに、教師自身がAIを適切に取り入れ、生徒ごとの学習を最適化するためのトレーニングも不可欠です。
生成AIは教育を効率化するツールにとどまらず、学びの本質を揺さぶる存在でもあります。これからの教育は、AIに任せる部分と人間が担うべき価値創造の領域を明確にし、両者の強みを融合させることが未来の学びを形づくる鍵となりそうです。
プロフィール

末岡 洋子(ITジャーナリスト)
アットマーク・アイティ(現アイティメディア)のニュース記者を務めた後、独立。フリーランスになってからは、ITを中心に教育など分野を拡大してITの影響や動向を追っている。
タグ
- アーキテクト
- アジャイル開発
- アプリ開発
- インシデントレスポンス
- イベントレポート
- カスタマーストーリー
- カルチャー
- 官民学・業界連携
- 企業市民活動
- クラウド
- クラウドインテグレーション
- クラブ活動
- コーポレート
- 広報・マーケティング
- 攻撃者グループ
- もっと見る +
- 子育て、生活
- サイバー救急センター
- サイバー救急センターレポート
- サイバー攻撃
- サイバー犯罪
- サイバー・グリッド・ジャパン
- サプライチェーンリスク
- システム開発
- 趣味
- 障がい者採用
- 初心者向け
- 白浜シンポジウム
- 情シス向け
- 情報モラル
- 情報漏えい対策
- 人材開発・教育
- 診断30周年
- スレットインテリジェンス
- すごうで
- セキュリティ
- セキュリティ診断
- セキュリティ診断レポート
- 脆弱性
- 脆弱性管理
- ゼロトラスト
- 対談
- ダイバーシティ
- テレワーク
- データベース
- デジタルアイデンティティ
- 働き方改革
- 標的型攻撃
- プラス・セキュリティ人材
- モバイルアプリ
- ライター紹介
- ラックセキュリティアカデミー
- ランサムウェア
- リモートデスクトップ
- 1on1
- AI
- ASM
- CIS Controls
- CODE BLUE
- CTF
- CYBER GRID JOURNAL
- CYBER GRID VIEW
- DevSecOps
- DX
- EC
- EDR
- FalconNest
- IoT
- IR
- JSOC
- JSOC INSIGHT
- LAC Security Insight
- NDR
- OWASP
- SASE
- Tech Crawling
- XDR